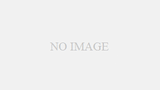生活保護は「資産がない人だけが受けられる」と思っていませんか?
実は、持ち家があっても条件次第で受給できるケースがあります。
しかし、評価額が2000万円クラスになると、自治体やケースワーカーの判断は厳しくなり、売却を求められることも少なくありません。
この記事では、持ち家2000万円でも生活保護を受けられる条件や資産評価の基準、売却回避の方法、実際の体験談までわかりやすく解説します。
制度の仕組みを正しく理解し、後悔しない選択をするための知識を身につけましょう。
生活保護と持ち家の関係を正しく理解する 🏠
生活保護は「資産がない人」が対象というイメージがありますが、実は持ち家があっても受給できる場合があります。
ただし、その家の価値や状況によって判断が変わります。
生活保護の基本条件は「働けない、または働いても最低限の生活費に満たない」こと。 そして、預貯金や不動産などの資産を生活費に充てられる場合は、まずそれを使うというのが原則です。
持ち家の場合、居住用として使っているかどうかが大きなポイント。 空き家や貸家は「売却して生活費に充てられる資産」とみなされやすいですが、自分が住んでいる家は例外的に認められることがあります。
ただし、資産価値が高すぎる場合(例:2000万円)は、売却を求められる可能性が高まります。 自治体やケースワーカーの判断によっては、「その家を売れば生活できる」と見なされることもあります。
私が以前、福祉事務所で相談したときも、担当者から「評価額が高いと難しい」とはっきり言われました。 しかし、高齢や病気などで引っ越しが困難な場合は例外が認められるケースもあるとのことでした。
つまり、持ち家があっても絶対に生活保護が受けられないわけではありません。 「居住用か」「資産価値はいくらか」「生活の継続が困難か」がカギになります。
持ち家2000万円でも生活保護を受けられるケース ✅
「2000万円の家があるのに生活保護?」と思う人もいるかもしれません。 でも、実際には条件を満たせば可能です。
まず、居住用財産として認められる場合。 これは「その家に住み続けることが生活の安定に必要」と判断されたときです。 例えば、高齢で引っ越しが健康に悪影響を与える場合や、障害があって環境の変化が難しい場合などです。
また、住宅ローンが残っている場合は、家の評価額からローン残高を差し引いた額が資産価値とされます。 例えば、評価額2000万円でもローンが1500万円残っていれば、実質的な資産は500万円とみなされます。
私の知人は、築年数が古く評価額は高くても、実際には売却しても生活費が長く持たないと説明し、受給が認められました。 「机上の評価額」と「実際の生活可能性」は別物ということです。
さらに、自治体によってはリバースモーゲージ制度を活用し、家を担保に生活費を借りながら生活保護を受けるケースもあります。 これは家を手放さずに資金を得られる方法ですが、条件やリスクもあるため慎重な判断が必要です。
自治体ごとに固定資産税評価額の上限が決まっているようです。詳細は近くの福祉事務所に聞いて見てください。
実体験から学ぶ申請の流れと注意点 📄
私が福祉事務所に相談したときの流れを紹介します。
まず、電話で「持ち家があるが生活が苦しい」と伝えると、面談の予約を案内されました。
面談では、収入・支出・資産の状況を細かく聞かれます。 持ち家の場合は固定資産税の課税明細書や、不動産の評価証明書を提出する必要があります。
担当者からは「評価額が高いと売却を求められる可能性がある」と説明されましたが、私は高齢の母と同居しており、引っ越しが健康に悪影響を与える可能性を医師の診断書で証明しました。
結果、条件付きで生活保護が認められました。 ただし、「将来的に売却可能な状況になれば再検討する」という条件付きです。
この経験から感じたのは、事前準備がとても大事ということ。 必要書類を揃えるだけでなく、なぜその家に住み続ける必要があるのかを具体的に説明できる証拠を用意することが重要です。
売却を求められるケースと回避策 💡
持ち家の評価額が高い場合、生活保護の申請時に「条件を満たしたら保護は開始するけど、売れたら収入認定して下さい」と言われることがあります。収入認定した場合は、遡って精算することになります。
持ち家を持っていてもすぐに売却する必要はなく、お金がなければ先行して生活保護を開始することができます。すぐに売却しなければいけないと思っている人が多いですが、誤解です。
すぐに現金化できない車も同様です。
高齢であるとリバースモーゲージを求められることもあります。 これは家を担保に金融機関から生活費を借り、亡くなった後に家を売却して返済する仕組みです。 ただし、利用できる年齢や地域が限られます。
もう一つは、資産価値を下げる要因を正しく評価してもらうこと。 築年数や立地条件、老朽化の程度によっては、実際の売却価格が評価額より大幅に低くなることがあります。 不動産会社の査定書を複数取り、現実的な価値を提示するのも有効です。
私の知人は、家の老朽化や立地の不便さを写真と査定書で示し、評価額を下げてもらった結果、売却指導を免れました。
専門家と相談して最適な選択をする 🤝
生活保護と持ち家の問題は、法律・福祉・不動産の知識が絡む複雑なテーマです。 一人で判断せず、弁護士・司法書士・ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することをおすすめします。
特に、自治体ごとに判断基準が微妙に異なるため、地元の福祉制度に詳しい専門家が心強い味方になります。 無料相談会や法テラスを活用すれば、費用をかけずにアドバイスを受けられる場合もあります。
私自身、弁護士に相談したことで「この条件なら受給の可能性がある」と背中を押され、安心して申請に臨めました。 結果的に、精神的な負担も大きく減りました。
最後に、生活保護は「最後のセーフティネット」です。
持ち家があっても、生活が成り立たない状況なら、ためらわず相談することが大切です。
正しい知識と準備があれば、家を守りながら生活を立て直す道も見えてきます。
✅ まとめ
持ち家が2000万円あっても、居住用として必要性が高い場合や、実際の売却価値が低い場合は生活保護が認められる可能性があります。
重要なのは、資産評価の仕組みを理解し、必要な証拠や書類を揃えて申請に臨むことです。
また、リバースモーゲージや専門家相談など、売却以外の選択肢も検討することで、家を守りながら生活を立て直す道が開けます。
生活保護は最後のセーフティネット。
正しい知識と準備が、あなたの暮らしを守る力になります。