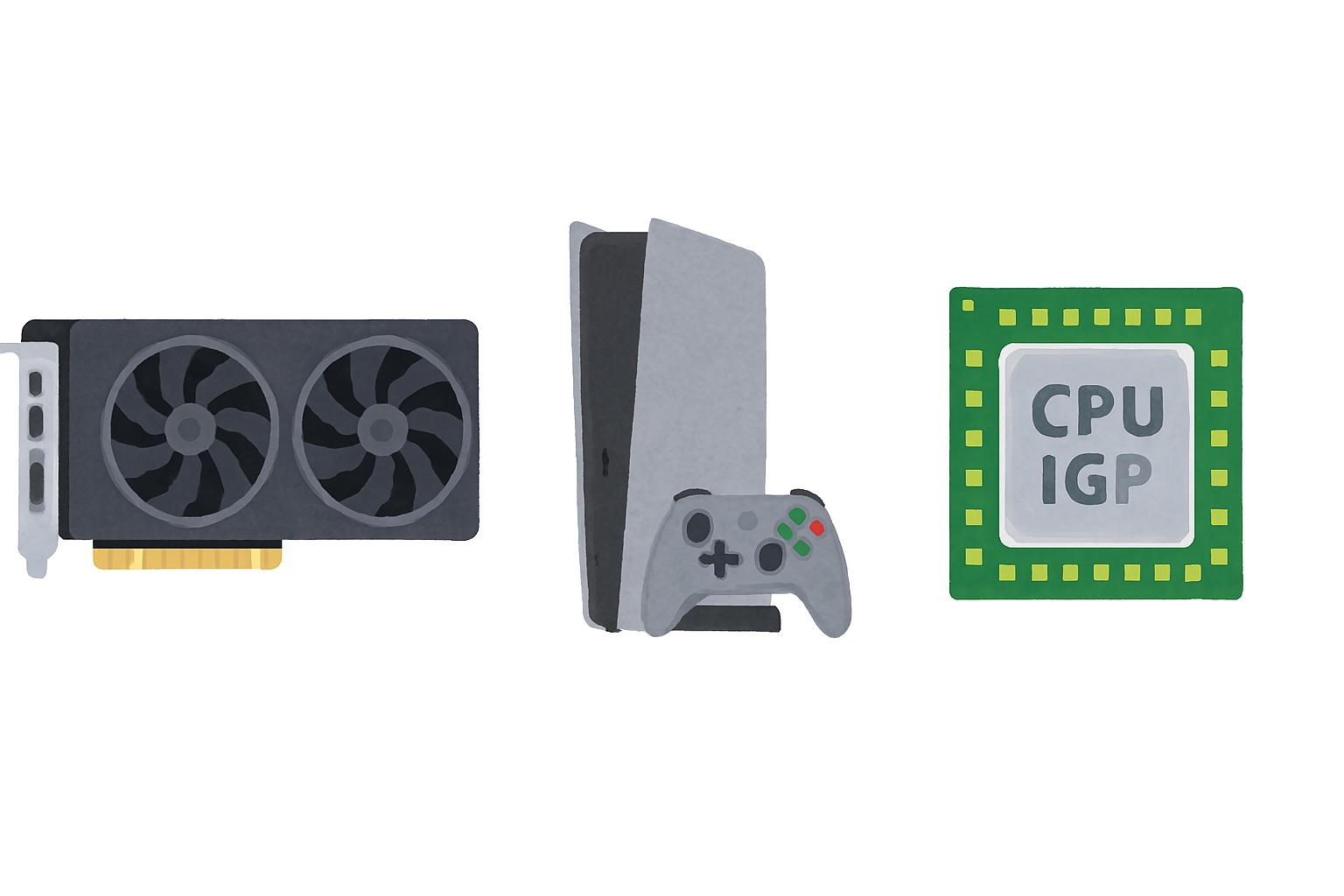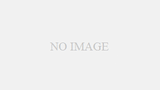グラフィックボード(グラボ)の価格、ここ数年で驚くほど高くなりましたよね。
昔は最上位モデルでも10万円以下で買えたのに、今では20万円超えも珍しくありません。
しかもグラボは陳腐化が早く、現役でいられる期間が短いのも事実。
「じゃあゲーム機のほうがコスパいいの?」と思うかもしれませんが、やりたいゲームがPC専用で高画質・高フレームレートを求めるなら、今でも高性能グラボは必須です。
この記事では、グラボが高い理由や価格高騰の背景、安く買うコツまで、体験談を交えてわかりやすく解説します。
グラボが高いと感じる瞬間と背景
「え、こんなに高いの?」 久しぶりにPCパーツショップを訪れたとき、私は価格表を二度見しました。 昔は最上位モデルでも10万円以下で買えた時代があったのです。 2010年代前半のハイエンドGPUは8〜9万円台で手に入り、それでも「高い」と感じていました。
しかし今では、最上位モデルは20万円を超えることも珍しくありません。 ミドルレンジですら10万円近くすることもあります。 この価格差は、PCゲーマーや動画編集者にとって大きな負担です。
私が初めて自作PCを組んだとき、グラボは予算の3割程度でした。 ところが最近は、グラボだけで予算の半分以上を占めることもあります。 これでは「PCを新調しよう」という気持ちも萎えてしまいますよね。
背景には、半導体不足や需要増加など複数の要因が絡んでいます。 そして、単なる物価上昇以上に、市場構造の変化が価格を押し上げているのです。
グラボが高い主な理由
グラボが高騰している理由は一つではありません。 まず大きいのが半導体不足です。 世界的な需要増加と供給制限により、製造コストが上がっています。
さらに、マイニング需要も価格高騰に拍車をかけました。 暗号資産の採掘に高性能GPUが使われ、ゲーマーとマイナーが同じ製品を奪い合う状況になったのです。
加えて、円安や輸入コストの上昇も日本国内の価格を押し上げています。 海外では同じモデルが安くても、日本に入ってくると為替の影響で高額になります。
ここ数年で同じ性能帯の価格が1.5〜2倍になった印象です。 しかも、性能向上のペースは鈍化しており、「値段の割に性能が伸びない」と感じる人も増えています。
陳腐化の早さとコスパの悪さ
グラボは陳腐化が非常に早いパーツです。 10年前のハイエンドGPUは、今ではCPU内蔵のiGPUに性能で追いつかれています。 当時10万円近く払って手に入れた最強モデルが、今ではエントリークラス以下の性能しかないのです。
私も昔、ハイエンドモデルを購入して「これで5年は戦える!」と思っていました。 しかし3年後には最新ゲームで設定を下げないと快適に遊べなくなり、結局買い替えることに…。 現役でいられる期間が短い=トータルでコスパが悪いと痛感しました。
さらに、新世代モデルが出るたびに旧モデルの価値は急落します。 中古で売っても、購入時の半額以下になることがほとんどです。 長期的に見れば、グラボは「高くて寿命が短い贅沢品」と言えるかもしれません。
内蔵GPUの急成長と10年前のハイエンド超えの現実
ここ10年で、CPU内蔵GPU(iGPU)の性能は驚くほど進化しました。 昔は「内蔵GPU=最低限の映像出力」というイメージが強く、3Dゲームはほぼ不可能でした。 しかし現在では、最新のIntel Arc搭載iGPUやAMDのRDNA系統の内蔵グラフィックスは、フルHDの軽量ゲームなら快適に動かせるレベルに到達しています。
特に衝撃的なのは、10年前の巨大で高価だったハイエンドグラボを性能で上回っているという事実です。 例えば、2013年頃のハイエンドGPUは、当時10万円近くし、補助電源や大型冷却ファンを必要とする“モンスター級”の存在でした。 それが今では、CPUに標準で組み込まれた小さなiGPUが同等以上の性能を発揮します。 しかも消費電力は圧倒的に低く、発熱や騒音もほとんどありません。
私自身、昔使っていたハイエンドグラボ(長さ30cm近く、重量1kg超)を押し入れから出してきて、最新のノートPCのiGPUとベンチマーク比較をしたことがあります。 結果は…最新iGPUの圧勝。 当時は「これ以上の性能は数年先」と思っていたのに、わずか10年で小型・低消費電力の内蔵GPUが追い抜いてしまったのです。
もちろん、最新のAAAタイトルを最高画質で遊ぶにはまだ専用グラボが必要です。 しかし、軽めのゲームや動画編集、日常的なクリエイティブ作業なら、もはやiGPUで十分な時代になりつつあります。 この進化は、グラボの必要性や買い替え判断にも大きな影響を与えています。
ローエンドグラボの需要は「性能」ではなく「画面出力」
グラフィックボードと聞くと、最新ゲームを高画質で動かすための高性能パーツというイメージが強いですが、GT710のようなローエンドGPUにも根強い需要があります。 その理由は、性能ではなく「画面出力」や「保守目的」に特化して使われているからです。
GT710は、2014年頃に登場したエントリーGPUで、ゲーム性能はほぼ期待できません。 実際、最新の内蔵GPU(iGPU)よりも性能が低いというのが現実です。 たとえば、Intelの第12世代以降のiGPUや、AMDのRyzen APUに搭載されたRDNA系統のグラフィックスは、GT710を大きく上回る描画性能を持っています。
つまり、GT710は「グラボなのに内蔵GPU以下の性能」という、ある意味特殊な立ち位置にあるのです。 それでも需要があるのは、映像出力端子が豊富で、古いモニターとの接続に便利だから。 HDMI・DVI・VGAなど複数の端子を備えているため、マルチモニター環境の構築や業務用PCの再利用に最適です。
特に、CPUに内蔵GPUがないモデル(IntelのFシリーズなど)では、画面を映すためだけにグラボが必要になります。 このようなケースでは、GT710のような低価格で安定動作するモデルが重宝されます。
私も以前、古い業務用PCを再利用する際にGT710を使いました。 目的は「画面が映ればOK」で、性能はまったく求めていませんでした。 結果として、消費電力が低く、発熱も少なく、静音性も高いので、オフィス用途には最適でした🖥️
また、企業や学校などでは、保守目的で同じ型番のグラボを複数台ストックしておくこともあります。 新しいGPUに変えるとドライバの互換性や設定変更が必要になるため、あえて古いモデルを使い続けるのです。
つまり、GT710のようなローエンドグラボは、「映ればいい」「安定して動けばいい」というニーズに応える存在。 ゲーミング用途とはまったく異なる価値があるのです✨
|
|
価格高騰の裏側にある市場の動き
グラボ市場は、新製品発表のたびに価格が大きく動く特徴があります。 新世代が出ると旧モデルは値下がりしますが、在庫が少ないと逆に値上がりすることもあります。
また、世界的な需要増加も影響しています。 ゲーミングPCやクリエイター需要だけでなく、AI開発や映像処理など、GPUを必要とする分野が急拡大しているのです。 これにより、供給が追いつかず価格が高止まりする傾向があります。
新製品発表直後は価格が高く、半年〜1年後に落ち着くパターンが多いですが、最近は落ち着く前に次世代が発表されることもあり、安く買うタイミングが難しくなっています。
私が実践したグラボを安く買う方法

私が試して効果的だったのは、型落ちモデルや中古市場の活用です。 最新モデルにこだわらず、1世代前の上位モデルを狙うとコスパが良くなります。
また、セール時期やキャンペーンを狙うのも有効です。 特に年末年始や新学期シーズンは値引きが多く、ポイント還元も期待できます。
さらに重要なのは、必要性能を見極めることです。 自分が遊ぶゲームや使うソフトに合わせて、オーバースペックを避けることで無駄な出費を減らせます。
そして、もしやりたいゲームが家庭用ゲーム機で遊べるタイトルなら、思い切ってゲーム機を選ぶのも一つの手です🎮 最新のゲーム機は5〜7万円程度で購入でき、数年間は安定して最新ゲームを楽しめます。 PC用グラボのように短期間で価値が大きく下がることも少なく、コスパ面では非常に優秀です。
|
|
|
|
ただし、やりたいゲームがPC専用で、しかも高画質・高フレームレートでプレイしたい場合は、今でも高性能グラボが必須です。 特に最新のAAAタイトルや高解像度モニターでのプレイでは、内蔵GPUや低価格帯のグラボでは性能が足りません。 この場合は、価格と性能のバランスを見極めつつ、納得できるモデルを選ぶことが重要です。
もし、あなたが遊びたいゲームが家庭用ゲーム機でもプレイ可能なタイトルなら、迷わずゲーム機を選ぶのがおすすめです🎮 ゲーム機は本体価格が5〜7万円程度と比較的安く、グラボのように短期間で価値が下がることも少ないため、コストパフォーマンスに優れています。 しかも、最適化された環境で安定してプレイできるので、設定やドライバに悩まされることもありません。
「PCでしか遊べない」「MODを入れたい」「高画質で144fps以上でプレイしたい」など、こだわりがある場合はもちろんグラボが必要ですが、そうでないならゲーム機のほうが手軽で快適です。 目的に合わせて選ぶことが、後悔しない一番の方法です✨
今後の価格動向と買い時の見極め方
今後のグラボ価格は、半導体供給の改善や為替の動きに左右されます。 円高が進めば、日本国内の価格も下がる可能性があります。
買い時を見極めるポイントは、新製品発表のタイミングです。 発表直後は高値ですが、数カ月後に価格が落ち着くことが多いです。 ただし、在庫が少ない場合は逆に値上がりすることもあるので注意が必要です。
私の経験では、「欲しいと思ったときが買い時」という考え方も大事です。 待ちすぎて価格が下がらないまま次世代が出ると、結局タイミングを逃してしまいます。
まとめと私の結論
グラボが高い理由は、半導体不足や需要増加、為替の影響など複数あります。 さらに、昔は10万円以下で買えた最上位モデルが、今では20万円超えという価格差も衝撃的です。
そして、陳腐化が早く現役期間が短いため、長期的に見るとコスパは悪いパーツです。 だからこそ、型落ちや中古を賢く活用し、必要性能を見極めることが重要です。
やりたいゲームが家庭用ゲーム機で遊べるなら、ゲーム機のほうがコスパが良くおすすめです。 しかし、PC専用タイトルや高画質・高フレームレートでのプレイを求めるなら、今でも高性能グラボは必須です。 価格の背景を理解し、自分の用途に合った選択をすれば、高い買い物でも後悔せずに済みます💡
|
|